
ファシリテーター ◉ 沖山尚美(プログラムオフィサー)
手を差し伸べる人のいる孤独・孤立から抜け出せる社会へ

2021年度 国内助成プログラム「互助を軸とした音声SNSプラットフォーム
 」代表者
」代表者それぞれの活動のあらまし
高原 セーフティネットリンケージの高原です。よろしくお願いします。唐突な質問ですが、認知症の方が迷子になって警察に捜索依頼届が出る数は年間どれくらいだと思いますか。
菰田 実際に僕の祖母が警察にお世話になった経験があります。
高原 その1件も含め、年間約2万件です。
渡辺 2万件もあるのですね。
高原 さらに、どんどん増えてきています。私の祖父が認知症でそういう経験があったので、みんなで見守る町ができたらいいなということがきっかけで、アプリを作ろうと思い立ちました。
このアプリは「見守り支援・多世代型」をキーワードに、地域の人に捜索依頼が簡単にできて、皆さんに探してもらう仕組みになっています。多世代型の見守り訓練ということで、絵本の『ウォーリーを探せ』みたいな楽しさの要素を入れているのがポイントです。町のイベントやお祭りでお母さん方に参加してもらうと、95%の方がこのアプリはお子さまの緊急事態にも使えると察するんです。そういう気付き、察することを僕は「微弱エネルギー」と呼んでいますが、こういう優しいエネルギーを積み上げてDX(デジタル・トランスフォーメーション)の仕組みとして担えればいいなと考えています。
今年から多文化共生という部分に着目しています。去年、地域の視える化ということで多世代や若い方にDXがどんどん広がっていくように同じアプリをスタンプラリーにしてデジタル版にしたのですが、それには音声ガイドも付けました。この人に会いたいなと声で巡れる町ができたらいいなという感じで、去年、大阪府の支援で60団体が集まって行いました。
今年からは74か国語ビジネス翻訳をこれに投入します。国内のAIを使うのですが、誰一人置いてきぼりにしない福祉のSNSになる予定です。このアプリは同時通訳がついているので、在日外国人、訪日外国人、日本人、誰もが言語を気にする必要がありません。通訳のスピードは平均2秒といわれていますが、このアプリは1・2秒から1・7秒。同時通訳を目指しています。また、日本には紙のチラシがたくさんありますが、そのようなものも添付しただけで自動翻訳されます。こういう福祉専用のSNSを今作っています。
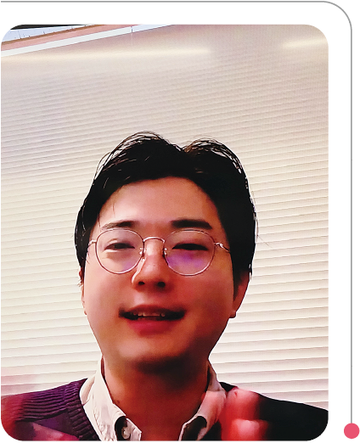
2023年度 研究助成プログラム「ひきこもり当事者と地域プラットフォームの協働に基づく新しい価値観と社会システムの構築
 」代表者
」代表者
菰田 鳥取大学地域学部で教員をしております。菰田と申します。
鳥取大学は全国で初めて地域学部を作った大学です。地域学部について分かりやすくいうならば、学識経験者といわれるような研究者だけが研究をしていたり、研究者だけが優位な知識を持っていて、地域に住んでいる方々はそれに従うべきだとか、それに沿って行動を変えてくださいという学部ではありません。そうではなく、地域の人たちも実はさまざまな知識を持っているので、一緒に学び合うために地域へ出ていこうという学部です。
海、山、中山間地域それぞれにいろいろな知識やノウハウがあるんですよね。そういう活動を2000年代初めから行ってきた大学なんです。
助成プロジェクトに関しては、2021年にこの大学に赴任した時に地域の方からご相談があったのがきっかけです。鳥取県西部の米子市に「総合相談支援センターえしこに」という、どんな相談でも受けますという窓口ができたのですが、開所してみたら年間で約500件の相談があり、そのうち広義の引きこもりに関する相談が延べ90件ほどありました。そのときに米子市役所のソーシャルワーカーや社協の方々がいろいろと考えた結果、引きこもっている人たちをなんとかして社会に出せばいいとか、すぐ就労につなげればいいというような簡単な話ではないということに現場の方々が気付いて、どうすればいいんだろうと困ってしまったわけです。そこで鳥取大学医学部の臨床心理の先生と、もともと生活困窮者自立支援法などの分野で仕事をしてきた私のところに相談が来ました。
まずは困りごとからみんなで話して、どのようなアプローチが必要なんだろうかとか、そもそもどういうふうに地域の中で実践を進めていけばいいんだろうかという話になった時に、たまたまトヨタ財団の募集を見つけました。トヨタ財団の助成はただ研究するだけではなく社会実装にも理解があるようだったので、現場の方と、いわゆる学識経験者である私たちが一緒になって地域を変えていくような、アクションリサーチ型のプロジェクトを進めたいと思い、応募したのが始まりです。
引きこもりのご本人たちに、これからどんな社会だったら自分にとって生きやすいだろうかというようなお話をお聞きしたり、逆に、引きこもりを見つめる地域の方々がどういう意識を持たれているのかを調べたり、あとは地域の中でこうしたことに関心を持ってくれるサポーターを広げるためのワークショップのようなことを意図的に仕掛けながら、いろんな機関と連携しながら活動を進めているところです。
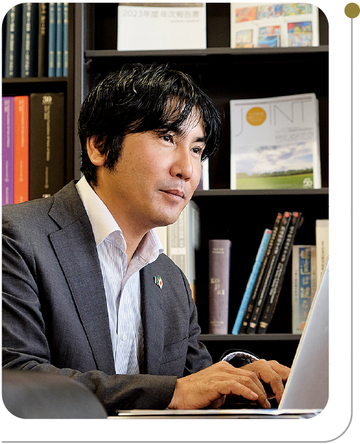
2022年度 国際助成プログラム「社会的な保護へのアクセスが困難な子どもたちのメンタルヘルスとその対策に関する研究調査─バングラデシュと日本の子どもを例に
 」(代表者:菅谷亮介)
」(代表者:菅谷亮介)渡辺 私は現在、一年の350日はバングラデシュにおりますが、22年前に大学を卒業してすぐ、ストリートチルドレンという存在の、抑圧されているような子どもたちに対して何かしたいという思いだけでバングラデシュに渡りました。言語を学ばないとはじまらないので、現地でダッカ大学のベンガル語学科に入り、そこで出会ったバングラデシュの仲間たちと立ち上げたのが「エクマットラ」という団体です。エクマットラとは一本の線という意味なのですが、非常に大きな格差が存在するバングラデシュで、いろんな世代、いろんなバックグラウンドを持つ人たちが共有できる一本の線を作りたいという思いから、この名前を付けて活動を始めました。
二つの活動が柱になっていますが、一つは直接的な支援で青空教室の運営、子どもたちが逃げ込めるレスキューセンターの運営などです。2018年に設立した全寮制の次世代のリーダーを養成していく学校の運営もしています。もう一つは、その活動だけをしていても物事が変わらないということをずっと痛感してきた22年間だったので、子どもたちが置かれている現状を紡ぎ合わせた、『アリ地獄のような街』という映画を作り、それをバングラデシュ、日本、ほかにも何か国かで上映しました。そこには、こういった問題に気付いてもらい、自分事として捉えてアクションにつなげてもらうという思いがありました。
この二つの活動を通じて大きな手応えを感じてきた一方、政策、枠組み、ルールがちゃんと作られていかないと、啓発や子どもたちの成長の支援だけでは限界があるなと思いました。大きなアドボカシー活動、政策提言、ルールや仕組み作り、または枠組み作りなどをしていくうえで、大きな調査をする必要があると考えました。調査項目として、衣食住といういちばん目に見える支援は分かりやすいので最初に出てくるのですが、どうしても路上生活をしている子どもたちのメンタルヘルスという部分には目が向きません。
途上国の子どもたちってたくましく見えるのです。実際にそういう面もありますが、親から捨てられたり、自分の実の母親から虐待されたりして路上に逃げてきた子どもは、表面上はたくましく見えても心に傷を持っているというのはすごく感じていました。でも、NGOですら衣食住の部分には目を向けていても、メンタルヘルスには向いていない。政府も、子どもたちに宿は提供したりしますが、その宿で性的な虐待が行われてしまったり、暴力が振るわれてしまったりする状態があるなかで、それぞれのセンターがどういうメンタルヘルスのカリキュラムを持ち、トレーニングを受けた施設スタッフが仕事をしていくかというルール作りが必要だなと思いました。
バングラデシュと日本という、社会的擁護を必要とする子どもたちが置かれた環境が大きく異なる二つの社会を比べることで学びあえることがあると考え、まずはその調査と、政策提言につながるリサーチをしていこうというなかで、先ほど菰田さんがおっしゃっていましたが、アクションに向いていながらリサーチもできる、すごく柔軟に活用できる助成金ということでトヨタ財団に応募しました。
楽しさと気付き、 この二つが人を動かす
高原 具体的にどのように居場所の支援をしたかについて補足させてください。アプリを多言語にしたと言いましたが、これには目的があります。無関心な人たちにどうやって意識が変わるきっかけをもたらすかというのが大切で、それには楽しさの要素があると入りやすいのですが、言葉が通じないとその楽しさを感じられません。今渡辺さんのお話をうかがってバングラデシュでお手伝いできることがありそうだなと思いました。それから去年、認知症家族の会に呼んでいただいて、鳥取で講演をさせてもらったご縁があります。
認知症と診断された方々にご協力いただく実証実験は、コロナ禍に重なってしまい当初の予定より小規模で行いましたが、担当のお医者さんには約60名中参加者が1割もいればいいのではと言われていたところ、実際には90%以上の方にご協力いただけました。小さなグループを作るとそこで心が開くということが分かったので、まずはそれを少しずつ育てる。一方で、面で広げる必要もあり、それには地域の人たちの意識を変えないといけないので、楽しさを打ち出して大学を巻き込んでスタンプラリーで町巡りをするようなイベントを行いました。これらがないと町って作っていけないのかなという、そういう取り組みをしています。
渡辺 バングラデシュでは昨年夏にとても大きな政変があったのですが、その時もインターネットを通じて誰がどういう思想を持っているのか、それを知られて個人を特定されて狙われたりすることがあってすごく危険を感じています。路上生活の子どもたちも含めて人が特定されて攻撃されるような非常に危険な状況をはらんできていると感じているので、福祉分野で安心して使えるSNSはバングラデシュでも非常に大事になってくると思います。
高原 今、インドでもプロジェクトが始まっています。いずれ社会を支援しようという志がある学生が多い大学で行っていますが、私たちの安心できるSNSに気付いてもらう仕掛けをしています。押し付けだと人間は動かないんですよね。楽しさと気付きがないと。
渡辺 今後引きこもりの人たちの支援もしていきたいと考えていますが、助成プロジェクトの一環で日本で若年層の居場所づくりを支援している団体を訪問させていただいて、そのご縁で、その後もずっとやり取りを続けてきています。日本の支援施設の方々が、そこで生活する日本の子どもたちがバングラデシュに行き、全然違う状況、環境の中で心に傷を持ったりしながらも前を向いてたくましく生きている子どもたちと触れ合うことが、ものすごくいい効果を生むんじゃないかということをおっしゃっていました。
もちろん、それが双方にとって悪影響にならないよう仕組みや防御体制を作る必要はあると思うのですが、それができたらものすごくいいきっかけになるだろうと思っています。しかも、日本というある意味ちょっと閉塞感のあるような社会の中で生きづらさを感じているような人たちにとっては、いいきっかけになるだろうと話しているところです。精神疾患などではなく高校受験や就職に失敗したようなところから引きこもってしまった方々にとって、全く違う環境、そして大の親日国であるバングラデシュに行って、そこでただ交流して終わるのではなく、現地の子どもたちがこれから立ち上がっていくことに自分たちが支援できる、自分たちが関われる、そういった当事者意識を持てることがあると、両方が立ち上がっていくきっかけになるだろうなと思っています。
菰田さんにお聞きしたいのですが、今、鳥取県で引きこもりの方々を対象にサポートされる際に、第三国、特に途上国と言われている国に子どもたちを送り込み、そこで化学反応を起こしていきたいという私たちのプランをどう考えられますか。かなり難しい病気を抱えて引きこもっている人たちは厳しいかもしれませんが、もう少しソフトな理由で引きこもりになってしまっている方々の入り口としてどうでしょうか。
菰田 鳥取大学に就任する前には、さまざまな生きづらさを抱えている方々を支援しているNPOや協同組合の研究してきました。その頃、池袋にあるNPO法人グッドという団体とお付き合いがありました。そこは引きこもりや、日本に生きづらさを抱えて悶々としている子たちを環境が全く違う外国に送るワークキャンプというのでしょうか、そのような実践をされている団体です。今のお話を聞いて、鳥取にはそういうことをしている団体はないので、お話をいただけたらやりたいという方がきっといらっしゃると思いました。
引きこもりに関わる全ての方々が関心を持つとは思いませんが、一部の当事者には非常に刺さるプロジェクトになると思うので、冗談抜きでご一緒したいです。
社会からの抑圧と孤独・孤立対策推進法
菰田 日本では教員や支援職に就いてる方々は個別の配慮が求められる場面が非常に増えてきていて、きめ細やかな配慮をしながら対応しなければならず、キャパの限界を超えて疲弊しているという現場の悲痛な声も多々聞きます。皆さんの現場ではそのあたりはどういう現状なのか、どういう対応をされているのか、教えていただけますか。
渡辺 私たちは、子どもたちも職員も住み込みで、24時間気が休まりませんでした。勤務時間は9~10時間ですが、住み込みなので勤務時間外でもずっと子どもたちの声は聞こえるし、何かがあったら駆け込んでくるので休まらないというところで疲弊は感じていました。そこで子どもたちがいる施設のすぐ外にもう1軒借りて、職員は休みになったらそちらに移動することにしました。
トヨタ財団のプロジェクトで日本からの学び合いというところで得た知見のひとつに、業務を分担していくということがあります。一人で抱え込まないで役割分担するということを私たちの団体の中でも取り入れて、絶対に抱え込み過ぎない、自分だけで向かわない、何かがあったらちゃんとパスを出せる体制をつくっていったところがすごく大きかったです。あとは子どもたちとの関係性についても、子ども個人対支援者個人にならないように、子ども個人対支援職員グループというようにしたことで、少しプレッシャーから解放されたと思います。資金的に限りがあるのでスタッフの数を増やすことはできなかったのですが、このような形で連携したりパス回しをするようになってから、少し変わってきました。
私たちは子どもの数に対する職員がバングラデシュのほかの団体に比べると多いほうなのでグループでの対応ができますが、ほかの団体では30~40人の子どもが寝泊まりしているところに職員1人というところもあります。それはもうパスを回す人もいないので、全部抱え込まないといけなくて、職員が暴力をふるってしまうといったような状況につながっているケースもあると思います。
── 社会的に起因していることを個人の努力で何とか乗り越えるというのは難しい、そういう機運もあって、政府も去年の4月に孤独・孤立対策推進法というのを施行したわけですが、この法律ができたことによって何か変わったり、追い風になったりしたことはありますか。また、変わりそうという期待できることはありますか。
菰田 鳥取県 孤独・孤立と検索していただくと、「鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある
支え愛社会づくり推進条例」という条例が出てくるのですが、実はこれ、全国初の孤独・孤立支援の条例として23年1月に施行されました。24年4月、ちょうどトヨタ財団の助成が始まった時期に国の法律として孤独・孤立対策推進法ができました。
県としては先駆けて条例を施行し、鳥取県で関係者のプラットフォームをつくり、また県内の実態を明らかにするため、県の職員が私たちのトヨタ財団のプロジェクトに関心を寄せてくださり、私たちのやっていることも含めて意見を言わせていただきました。その結果、私たちが作った調査の原案を鳥取県が採用してくれて、鳥取県民向けのアンケートにつながったということもありました。偶然ではありましたが、私たちの場合はこの条例が良い追い風となりました。
高原 僕らがキャッチにしている「一人でいても一人ぼっちにしないまちづくり」という言葉があります。一人でいること自体は全く問題なく、自分がそうしていたいなら一人でいていいんですよ。だから、孤独・孤立の定義が「一人でいること」となると違っていて、助けてほしいと思ったときに、もうそこにいるよというオープンな町を目指しています。がん患者さんの会がうちのアプリを使ってくれているんですけど、コロナの前はたくさんの人が集まって会っていたのに、コロナが明けたら集まらないのがもう習慣化してしまったそうです。そこで私たちのアプリを使ってがん患者さんだけの番組ラジオをつくったんです。サバイバーの人たちが自分の体験を語っていて、それにアクセスしてくれる。顔も名前も知らない人だけど、関係性ができると次のリアルに行きやすいと。
日本ではSNSなどインターネットから情報を取るのが一般的になってきていて、その傾向は若い人たちに特に顕著です。しかもマイナスの情報を取りやすくなってしまっているので、その影響もあるのか、いきなり面と向かって行くというのが苦手というか、心のステップがちょっと不器用になっているような気がしています。
認知症に関しても、SNSで情報を取りに行くんだけど、しんどくなって見なくなるというパターンなんです。そうするとアクセスする情報がないから悶々としてしまう。たまたま菰田先生みたいなすてきな先生に会うと、はっとして立ち上がれるけど、運悪く会わなかったら、そこでじっとしたままという。だから、ちゃんとしたSNSをつくると、まだ日本は何とかなるかなと感じているのですが、バングラデシュはどうでしょうか。
渡辺 バングラデシュは、コミュニケーションという点では相手の気持ちを考えるとかいう前に強引にでも言ってしまうところがすごく強いので、そういった意味では、コミュニケーションの希薄さというのは非常に少ないと思います。
だから、最初に言ったように、たとえば路上にいる子どもたちってものすごくたくましいんですよ。多分、日本で貧困の問題を抱えている子どもたちって疎外感を持ったり、周りと違うというところから、自分たちだけが孤立しているというふうに感じると思うんですけど、バングラデシュでは絶対数が非常に多いので、自分たちだけじゃないんですよね。周りを見たら自分と同じような状況の子たちがたくさんいるわけで、ある意味、自分たちはマジョリティーであるといったようは気持ちを持ちやすい。もちろん、そんな状態の子どもたちがマジョリティーでいるということ自体問題なのですが、そういった意味では心の問題が表面化しにくいです。
子どもたちはすごく明るいし、たくさんコミュニケーションしてくるし、とてもたくましくて強い。でも、心の問題がないわけではないので、ある時に突如出てきます。それが大きな犯罪だったり、いつも明るくてにこにこしている子が、いきなり人を殴ったとか刺したとかということが起こります。何かのスイッチ、トリガーが引かれると、はじけてしまって野獣になるという瞬間があるのです。そういう点では日本とはちょっと違いますよね。
助成プロジェクトの学び合いという中で、たとえばバングラデシュではそのトリガーになるのがどういう言葉かというのが体系化されていなくて、私たちを含め恥ずかしながら経験値だけでやってきていたのですが、そういったところがちゃんと仕組み化、体系化された日本の知見を共有していただけたのはすごく大きかったです。逆に、さっき言ったように日本の引きこもりの子たちがバングラデシュに来て、バングラデシュの子どもたちが社会から抑圧されているにもかかわらず、これだけプラスに変えられているという部分を感じることで、いい持ち帰りをできるんじゃないかなというところは感じています。
バングラデシュは日本の孤独・孤立対策推進法とは関係ないところにありますが、こういったことが法律として制定されたことによって、つながりが生まれる社会であったり、その人たちがもう一回社会復帰していくことを義務づけたということが、バングラデシュやほかの国々に人を送ることの後押しになっていったら、すごくいいなと期待感を持っています。
人が困っていたら助ける社会
── それでは最後に一言ずつ、本日の感想と、何を信じて今後の活動にあたっていきたいか、お話しいただけますか。
渡辺 私たちはどうしてもバングラデシュ目線でしか見えていない部分があったのですが、この助成プロジェクトで日本の知見を共有してもらったことですごく自分たちの活動の幅が広がったと感じていました。その延長でこうして今日お二方とお話しすることができて、バングラデシュで取り入れられるヒントがたくさんあるなと思いました。
自分が日本人として誇りを持っているなかでバングラデシュの人たちに向けて活動しているときに、日本に還元できていないというもどかしさがどこかであったのですが、バングラデシュというフィールドで、自分たちが守っている子どもたちというリソース、アセットと関わることで、日本の引きこもりの人たちをバングラデシュにお呼びするというような試みを通じて日本に成果を還元できたら、これほど嬉しいことはないなと思うので、ぜひともこのご縁を生かしていきたいと強く思っています。
路上の子どもたちには確かにいろんな抑圧された環境があるんですけれども、周りの心ある大人が寄り添ってしっかりとチャンスを提供していくと、私たちが信じられないような化学反応を起こして成長していくという場面をずっと見てきました。
この20年間活動してきたなかで、路上にいた子どもたちが過去を乗り越えて、大学生になり、卒業し、今度はその子がケアワーカーとなって私たちの活動を支えてくれたり、日本の商社の現地事務所に就職したり、大学の学部で首席を取ったり。そういう子どもたちが出てきています。その子どもたち自身が次の世代に対してメッセージを発信していくことができると、世の中の目が、子どもたちを弊害や課題ではなく、可能性として見ていくことになるのではないかと思っています。
子どもたちの可能性を信じ抜いて目を向けてそこに関わり続ける。それで大逆転劇を引き起こし続ける。それによって社会の目を変えていくということを信じ続けてやっていきたいなと思っています。
菰田 今日はバングラデシュに行く話やアプリの話など、鳥取で具体的にやれるかもしれないアイデアをいただけたので、こういう場に呼んでいただいて本当によかったなと思いました。
何を信じて動いていくかは非常に難しいですが、NPOなどがやっていることは、いかにいろんな人々の協力を引きつけていくことができるのか、協力をつくっていくことができるのかというところに基本的な本質みたいなものがあると思っています。各NPОごとに信念は異なるので、なので私は「何を」ではなく、その協力を広めていくためにはどうすればいいんだろうというところに問題、関心があります。
もう一つは、引きこもりの話もそうですが、実は僕自身の親戚も引きこもりという経験があって、こうしたことは誰にでも起こり得るということはいつも言い続けていきたいと思っています。今、引きこもりだけではなくて、たとえばハラスメントの問題も加害とか被害というのが、いつ何どきでも自分に起こるような社会になっているような気がしています。そんななかで、自分は関係ないというのではなく、いつ何どきでも起こり得るからこその前提に立ったときに、どんな社会をつくりたいのかというようなことを、まだうまく言葉にはできていないんですけれども、そんなことを日々考えながら動いていきたいと思います。
高原 今日はお二人とお話できて、バングラデシュでも鳥取でも一緒に具体的に取り組めたらなと思えるようなご縁をいただきありがとうございます。
僕らの団体は、最初株式会社にするか非営利にするかでとても悩みました。DXってスタートアップ企業として始めるのが普通で、投資家からお金を集めてやるという発想に反するトライというのが、多分世界でもこれまでになかったんです。だから非営利でやれるのかなと思ったときに、失敗しても僕が破産するくらいですむなら、やってもいいかなと思ってはじめてみたんです。
今考えるとものすごいリスクがあったのですが、不思議なのが、今日お二人に出会えたというのも僕の財産ですが、その時々で助けてくれる人がいたことです。でもそういう関係って簡単にはつくれなくて、お金はありませんがこういう思いでやりたいんです、と地道に言って活動していくなかで出会えました。非営利でスタートして間違っていなかったんですね。
非営利にした理由は、互助を使うという点を考慮したからです。人様の「微弱エネルギー」を使うのに、投資家に還元するというのはおかしい。であれば、これは国に還すべきことだということで、僕らは公益社団法人を目指して国に還元しようと思っています。だから、そういう意味では、何を信じて期待しているかというと、日本人の多くがそうであるように、当たり前のように落とし物を拾ったら届ける、当たり前のように人が困っていたら助けようとする。名前を名乗らない。そんな脈々としたこの日本社会の昔からの精神をきちんとDXで残して、未来へつないでいく役割を担えればと思っています。

公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No.48掲載
発行日:2025年4月8日
