研究助成
contribution
寄稿


著者 ◉ 那須識徳 (農協共済中伊豆リハビリテーションセンター リハビリテーション部 作業療法科)
- [プログラム]
- 2023年度 研究助成プログラム
- [助成題目]
- 傷病後の自動車運転中断者に対しての地域社会参加の支援体制構築
- [代表者]
- 那須識徳 (農協共済中伊豆リハビリテーションセンター リハビリテーション部 作業療法科)
傷病後の自動車運転中断者に対しての地域社会参加の支援体制構築
運転を中止することの問題
私が所属する農協共済中伊豆リハビリテーションセンターでは、1973年の開設当初より障害者の自動車運転に携わってきました。当センターでは、運転再開を希望する対象者に対してドライビングシミュレーターや敷地内の実車運転コースを利用し、年間約100名程度の患者様に運転評価を行っています。そのうち約6割程度の方が退院後に運転再開に至っていますが、4割程度の患者様はすぐに運転再開には至らない状況です。
「先生、お父さんが勝手に運転するって言うんです。なんとか説得してください」
ある患者様のご家族からの電話でした。多いときには1か月で数回の電話があり、何度も運転評価を行いましたが、最終的に運転再開には至らず、運転免許の期限が切れて支援が終了しました。
「運転ができないと何にもできない。友達にも会えないし釣りにも行けない」
支援終了時の面談での患者様の言葉は、今でも強く印象に残っています。
傷病後に自動車運転をやめざるを得ない人々の生活は、想像以上に孤立しているのかもしれません。自宅から病院へ、買い物へ、友人との交流へ─その移動が途絶えたとき、人は地域社会とのつながりを失い、生活の質は大きく揺らぐ可能性があります。厚生労働省のデータでは脳卒中の初発は65歳以上に多いとされており、高齢化が進む日本では、こうした問題は今後さらに広がっていくと考えられます。
問題の背景と課題

近年、脳卒中や高次脳機能障害を背景に運転を中断する人が増えています。運転を再開できる割合は3〜6割程度にとどまり、運転の中断を余儀なくされる方も少なくありません。しかし、運転をやめた後の生活設計を支援する仕組みは十分に整っていないのが現状です。特に地方や山間部では公共交通が乏しく、自家用車の喪失が即、社会参加の制限につながることも少なくありません。就労や買い物、通院、交流といった日常の営みが困難となり、身体的虚弱や心理的抑うつを招く可能性もあります。
さらに、運転中断の経緯にも注目する必要があります。私たちの調査では、自分の意思で運転をやめた人は前向きに生活を再構築できる傾向がある一方、医師や家族の判断で中断を迫られた場合には、生活満足度が著しく低下していました。このことは、運転中止に至るプロセスの中で、自己決定の機会をいかに確保するかという点が非常に重要であることを示しています。
プロジェクトの取り組み
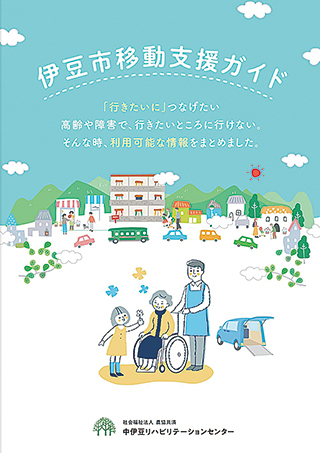
本プロジェクトは、トヨタ財団2023年度研究助成を受けて開始されました。テーマは「傷病後の自動車運転中断者に対しての地域社会参加の支援体制構築」であり、(1)教育、(2)情報提供、(3)代替移動手段の活用という三本柱を中心に展開しています。
第一に、当事者と家族への教育プログラムです。全4回の当事者セッションと1回の家族セッションを設け、「人─作業─環境」モデルや行動変容理論を用いながら、運転中断への準備性を高めることを目的としています(図1)。本人の不安や価値観だけでなく、送迎を担うご家族の心理的・時間的負担にも焦点をあて、対話を通じた納得感の形成を目指しています。
第二に、地域資源の可視化です。医療・介護・福祉・行政に分散した移動サービスは情報が煩雑であり、必要な支援に結びつかないことが少なくありません。そこで、近隣2市1町を対象に公共交通、福祉輸送、地域独自の移動支援を整理したパンフレットを作成し、当事者と家族が必要な情報に容易にアクセスできる体制を構築しています(図2)。
第三に、代替移動機器の導入です。シニアカーや電動車いす、電動アシスト自転車などの活用を念頭に、病院敷地内に段差や狭路、踏切を模した「モビリティコース」を整備しました(図3)。これにより、公道での危険を回避しつつ、安全な操作方法を学ぶ機会を提供しています。練習の効果や適応疾患を検証することで、シニアカーの評価方法の確立や練習方法の改良を進めていきます。
今後の展望と結び

本プロジェクトの根底には、これまでの研究の積み重ねがあります。代表者らは、後天性脳損傷後の運転中断者と家族の経験を質的研究で統合し、「人─環境─作業」モデルに基づいた支援の枠組みを提示してきました。
また、移動手段の変化に関する準備性を評価するARMTを日本語化し(ARMT-J)、信頼性と妥当性を確認しました。支援の枠組みを提示して介入方法を明確にし、運転中止までの準備性を高めることが、その後の生活にどのような影響を及ぼすのかを検証することも、本研究の目的の一つです。
今後は、教育プログラムを受講した群と従来支援群を比較し、地域参加やQOLへの効果を検証する予定です。さらに、作成したパンフレットやモビリティコースを利用して検証した知見は他地域や一般病院でも応用できるように、公開講座や研修を通じて社会へ広く普及させていきたいと考えています。
本プロジェクトの目的は、「運転ができなくなっても生活に困らない仕組み」を社会に示すことです。移動の困難さを見える化し、多様な生活の選択肢を提示することで、誰もが前向きに生活を再構築できるよう支援することを目指しています。これらの取り組みは、地域における生活の質の向上と社会参加の促進につながると考えています。
公益財団法人トヨタ財団 広報誌JOINT No. 49掲載
発行日:2025年10月21日
